2025年5月17日
災害ボランティアの安全確保:特殊梯子の正しい使用法と危険予知トレーニング

「被災地で何か力になりたい」
そんな思いで災害ボランティアに参加した経験がある方も多いのではないでしょうか。
倒壊した家屋の片づけ、泥のかき出し、物資の運搬など、ボランティアの活動内容は多岐にわたります。
中には、人命救助や仮設住宅の設営など、命に関わる重要な作業を担う場面もあります。
しかし一方で、こうした善意の活動が原因で、自らがケガを負ってしまうというケースも少なくありません。
たとえば、
- 瓦礫に足を取られて転倒した
- 濡れた斜面で滑って骨折した
- 無理に梯子を登って落下してしまった
こういった事故は、実際に多く報告されているのです。
特に「梯子からの転落事故」は、意外と頻発しており、最悪の場合には重傷にもつながりかねません。
そのため、災害ボランティアとして活動する際には「安全確保」を最優先に考えることがとても大切です。
そしてその鍵を握るのが、正しい道具の使い方と危険を予測する意識づくりなのです。
本記事では、災害現場で頻繁に使用される「特殊梯子(とくしゅはしご)」に焦点を当て、以下の3点を中心に解説していきます。
それではまず、災害ボランティア活動における安全対策の基本から見ていきましょう。
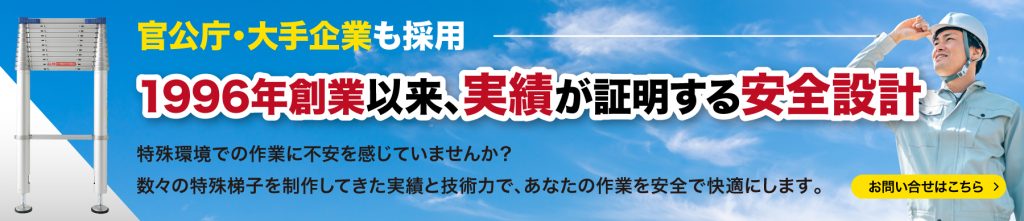
災害ボランティアにおける安全対策の基本
よくある事故例とその背景
災害ボランティアの現場では、「ちょっとした油断」が大きな事故につながることがあります。
実際、全国社会福祉協議会の平成25年度ボランティア活動保険事故報告によれば、最も多いのが転倒事故(約60%)であり、続いて転落(約9%)や交通事故(約11%)といったデータが示されています。
一見すると「滑って転んだだけ」と思われがちですが、被災地の足場は通常の現場とは大きく異なります。
- 地盤が緩んでいてぬかるんでいる
- 建物の残骸や瓦礫が散乱している
- 雨天や余震によって突然状況が変わる
このような不安定な環境下で作業を行うことが、事故リスクを高める要因になっているのです。
また、普段使い慣れていない道具、たとえばチェーンソーや特殊梯子などを使う場面も増えます。
「急いで作業しよう」「自分一人で何とかしよう」という意識が、かえって危険を招くこともあります。
装備の不備や安全確認不足が積み重なると、「まさか自分が」という事態が起こりうるわけです。
実際、SNSやボランティア団体のレポートを見ていても、
「梯子をかけた場所が不安定で、上から落ちてしまった」
「段差を踏み外してひざを痛めた」
といった声は決して少なくありません。
ここで重要なのは、「災害時の作業現場には、通常とは違うルールが必要だ」という意識です。
災害現場の特殊性と安全行動の原則
では、災害現場ではどのような安全行動が求められるのでしょうか?
まず押さえておきたいのが、現場は「通常の工事現場」とは全く異なる条件下にあるということ。
以下のような特徴を持っています。
- 足場が不安定:地盤沈下、瓦礫、泥、段差の連続
- 視界が悪い:倒壊建物の影、電力喪失による照明不足
- 予測不能な余震:突発的な揺れで作業中断の危険あり
- 支援人数が限られる:作業人数や役割が少数に偏りやすい
このような環境下で事故を防ぐには、以下の5つの基本行動が有効です。
1. ヘルメットや安全靴など、個人防護具(PPE)の着用を徹底する
→ 頭部・足元のケガを防ぐ第一歩です。
2. 必ず2人以上で行動する「複数人行動」の原則を守る
→ 一人で作業せず、異変があればすぐに助け合える体制を取ります。
3. 初動時には、現場の危険箇所を全員で確認する
→ 「ここは滑りやすい」「屋根の上は立ち入り禁止」などを共有。
4. 作業前には必ず声掛けと安全確認の「合図」を交わす
→ 「上がるよ!」「もう少し右に倒すよ!」などの一言が安全を生みます。
5. 疲れを感じたら必ず休憩をとる
→ 無理をして起きる事故が、実は一番多いのです。
これらの原則は、どれも難しいものではありません。
しかし「被災者を助けたい」という気持ちが強いと、つい自己判断で行動してしまう場面が出てきます。
だからこそ、安全対策は「知識」だけでなく「習慣」にしていくことが大切なんです。
特殊梯子の正しい使用法
特殊梯子とは?種類と特徴の解説
災害現場では、通常の作業用梯子では対応しきれないような状況が数多く発生します。
たとえば、
- 坂道や傾斜地
- 狭い路地や倒壊物の上
- 地下マンホールへの出入り口
- 避難用ルートとしての高所経路
こうした場面で活躍するのが「特殊梯子(とくしゅはしご)」です。
では、特殊梯子にはどのような種類があり、どのような特長があるのでしょうか?
代表的なタイプをいくつか見てみましょう。
1. 可搬型・伸縮式タイプ
軽量でコンパクトに収納できるタイプです。
車のトランクに収まるサイズ(90 cm程度)から、必要に応じて2 m〜7 mまで伸ばせます。
滑り止めゴムや壁当てクッションが標準装備されており、個人ボランティアにも使いやすい構造です。
狭いスペースでも展開でき、持ち運び頻度の高い現場で重宝されます。
2. 折りたたみ式(Z型)タイプ
数段の関節を折りたたんで収納できる構造で、障害物をまたいだり、段差のある場所でも設置が容易です。
Z型に広げることで足場の確保がしやすく、不整地でも安定しやすいのが特徴。
狭小地や瓦礫の上での活動時に適しています。
3. 多関節型(三態変形タイプ)
梯子の形状を「I型(直線)」「L型」「A型(三脚)」と切り替えられる多用途モデルです。
たとえば、マンホールへの縦の出入り、傾斜地への対応、地面が水平でない場所での作業に対応できます。
現場ごとに形状を変えられるため、土木・上下水道の復旧支援でのニーズが高いタイプです。
4. 避難用の固定・吊下げ式タイプ
避難経路として2階〜3階のベランダなどから使用するタイプ。
国家検定に合格しており、子どもや高齢者でも安心して使用できる設計です。
壁面に固定して収納でき、災害時に素早く展開できるのがメリット。
一時的な避難拠点の設営にも有効です。
これらの特殊梯子は、いずれも「一般的な作業用梯子」よりも、より現場対応力を求められる設計になっています。
一見すると大がかりな装備にも思えますが、実際には折りたたみ可能で軽量な製品も多く、ボランティアの携帯装備として十分に実用的です。
ここからは、そうした特殊梯子を専門に開発している当社の製品事例として、特殊梯子製作所有限会社が提供する製品ラインナップをご紹介していきます。
【製品紹介】災害現場に適した当社製品のご提案

当社は、安全機材専門メーカーとして長年にわたり、現場の声を反映した多様な梯子を開発・提供しています。
とくに災害現場や特殊環境下での使用に対応したモデルが揃っており、以下のようなシリーズがあります。
- SLシリーズ(スーパーラダー)
軽量アルミ製で、収納時の長さはわずか90 cm。
伸縮自在で、最大7.5 mまで対応可能。
持ち運びやすさと設置のしやすさにこだわった、ボランティア向けの基本モデルです。 - Gシリーズ
手掛棒、壁当てパッド、アウトリガー(横に広がる安定脚)を装備した安全強化型。
不整地や傾斜地での使用も安定しており、転落防止性能を重視した現場向けモデルです。 - TTMHシリーズ(TTマンホールはしご)
三態変形に対応するモデルで、地下マンホール作業や縦穴進入時に使用。
角度調整機構付きで、設置スペースの狭い場所でも柔軟に対応できます。 - QQラダー
避難用に設計された国家検定合格品。
火災や地震の際の高所脱出を想定しており、滑り止め付きステップや安全固定フックを標準装備。
高齢者施設や仮設住宅などにも設置しやすい構造です。 - オーダーメイド製品
鉄道の高架下作業、プラント内設備点検、タンク洗浄口など、特殊環境向けに1台から設計可能。
既存設備との干渉を避ける寸法設計が可能で、施工業者や自治体からの引き合いも多くあります。
これらの製品はいずれも「現場で使える安全性」を第一に設計されており、現場での負担軽減と事故防止に役立つ装備が標準化されています。
セッティングの手順とチェックポイント
どんなに高性能な梯子でも、設置や使用方法を誤れば事故の原因になってしまいます。
特に災害現場のような不安定な環境では、「正しく設置すること」そのものが安全の第一歩です。
ここでは、特殊梯子を使う前に確認しておくべきポイントを、実践的な手順に沿って紹介します。
1. 設置角度の目安を守る
梯子の最適な設置角度は 75度前後。
これは、地面から上方向に1メートル持ち上げるごとに、梯子の下端を壁から25cm離すという「1:4の法則」で表せます。
傾きすぎると転倒リスクが高まり、立てすぎてもバランスを崩しやすくなります。
角度が不安なときは、専用の角度計や水平器付きモデルを使うのが安心です。
2. 設置場所の状態を確認する
次に重要なのが「地面の安定性」です。
- 泥・ぬかるみ・傾斜地では滑りやすく、安定しにくい
- 凹凸や瓦礫があると、接地部分が浮いてしまうことも
こうしたときには、アウトリガー(横に広がる脚)や壁当て部材を活用し、可能な限り接地面を安定させることが大切です。
また、滑り止めゴムの摩耗や泥汚れがある場合は、事前に清掃または交換しておきましょう。
3. 使用前点検を行う
設置前には、以下の点を必ず確認してください。
- 梯子本体に変形・ひび割れ・歪みがないか
- リベットやボルトが緩んでいないか
- 関節部分がしっかりロックされているか
- 滑り止めが摩耗していないか
見た目だけでなく、手で触れて確認することが重要です。
とくに収納時に他の資材とぶつけた場合、目に見えないダメージがあることもあります。
4. 三点支持の原則を守る
梯子に上る際は、常に「三点支持」を心がけましょう。
これは、
- 両足+片手
- 両手+片足
のいずれかで、常に3点が接触している状態を維持することを意味します。
両手に荷物を持ちながら昇降するのは厳禁です。
必要があれば、ロープやプーリーで道具を地上から引き上げましょう。
5. 声掛けと補助体制を整える
安全確保には「声掛けの文化」が欠かせません。
- 「上がります」「下ります」「気をつけて」など、作業前に一言
- 梯子の下には、必ず補助者を配置してブレを防止
- 夜間や視界不良時には、LEDライトで手元を照らす
一人で黙って動き出すのではなく、「確認し合いながら」行動することが、事故の未然防止につながります。
以上のポイントを日常的に習慣化しておくことで、特殊梯子の使用リスクは大きく下げることができます。
危険予知トレーニング(KYT)の基本と応用
KYTとは?:現場での危険を見える化する手法
KYTとは「危険予知トレーニング(Kiken Yochi Training)」の略で、作業現場に潜む危険を事前に予測し、チームで共有して対策を立てる訓練のことです。
もともとは工場や建設現場で導入されてきた手法ですが、その有効性から、現在では医療、教育、さらには災害ボランティアの現場でも活用されています。
関連: 職場のあんぜんサイト:危険予知訓練(KYT)[安全衛生キーワード]
では、KYTとは具体的にどのような手順で行うのでしょうか?
もっとも基本的な方法として知られているのが、「4ラウンド法」です。
この4ステップを踏むことで、危険への感度が一気に高まります。
4ラウンド法の基本ステップ
1. 現状把握(どんな作業現場か?)
作業環境のイラストや写真を見ながら、「この現場にどんな危険が潜んでいるか」を全員で観察します。
→ 例:「この足場、傾いてないか?」「電線が近いかもしれない」
2. 本質追究(なぜそれが危険か?)
見つけた危険を「どんな事故につながるのか」という視点で深掘りします。
→ 例:「梯子が滑れば、作業者が落下するリスクがある」
3. 対策樹立(どう防ぐか?)
「その危険を避けるには、どんな対策が必要か」を全員で出し合います。
→ 例:「滑り止めをチェックする」「補助者をつける」「夜間は使用しない」
4. 目標設定(今日の安全目標)
最後に、当日の行動指針として「今日の目標」を決めます。
→ 例:「声掛けと三点支持を徹底しよう」
このように、KYTは単なる「注意喚起」ではなく、
「気づき」→「深掘り」→「行動」までをチームで共有できる仕組みなのです。
また、KYTでは専用のテンプレートやイラスト教材を活用すると、視覚的に危険をとらえやすくなり、初参加者でも理解しやすくなります。
災害ボランティア活動におけるKYTの活用例
災害現場では、毎回異なる作業場所・参加メンバーとなることが多く、そのたびに「安全意識を短時間で共有する方法」が求められます。
そんなときに効果的なのが、災害支援向けにアレンジされたKYTの実践例です。
【活用例1】現場到着前の5分KYTミーティング
作業を始める前に、リーダーが集まってその日の作業内容を確認。
「現場の危険は何か?」「どの装備が必要か?」を5分で話し合うだけでも意識が大きく変わります。
【活用例2】作業区画ごとのKYTチェックシート
現場を複数の小エリアに分け、それぞれにチェックシートを用意。
代表者が書き込みながら危険箇所を記録していくことで、現場ごとの特性に即した対策が可能になります。
【活用例3】4ラウンド法を簡易化した「ホワイトボードKYT」
道具置き場や本部テントにホワイトボードを設置し、
「今日の危険」→「予防策」→「目標」の3項目を自由に書き込めるスペースを用意。
交代制で記入・更新することで、現場全体の安全意識を底上げできます。
KYTのポイントは、形式にこだわるのではなく「考える習慣をつくること」です。
難しい手順や専門的な言葉を使わずとも、「この作業、ちょっと危ないかも?」という感覚を全員が持てるようになるだけで、災害現場での事故リスクは格段に下がるのです。
安全意識を高める工夫と継続的な学び
現場での「声掛け」と「気付き」の文化
安全な現場づくりに欠かせないもの――それが「声掛け」の習慣化です。
「はい、確認しました」
「ちょっと危ないかも、気をつけて」
「一人で持てる?手伝おうか?」
こうした些細なやり取りこそが、事故の芽を摘む“生きた安全対策”になるんです。
実際、事故が少ない現場では、作業者同士のコミュニケーションが活発であることが共通しています。
これは「ヒューマンエラーを防ぐ」という意味でも非常に重要です。
人は慣れてくると、手順を省略したり、自分の判断で動いてしまいがちです。
そんなときに誰かが一言声をかけてくれるだけで、事故を未然に防げるケースは少なくありません。
また、災害ボランティアの現場では、初対面の人と協力することも多いため、名前を呼び合いながら作業することも安全管理の一環となります。
🔍現場で実践されている工夫例
- 朝礼時に「今日の安全行動宣言」を行う
- 名札やビブスに「名前+班名」を明記
- 作業中は「○○さん、声掛けOKですか?」と話しかけるルールを設ける
- 子どもや高齢者のボランティアには、リーダーが付き添う体制を整備
さらに、ベテランの「気付き」や「ヒヤリ体験」を新人と共有する仕組みを導入することで、現場の安全意識はより強固になります。
たとえば、作業後に「気になったこと」「危なかったこと」を一言メモに書いてホワイトボードに貼るだけでも、次の活動へのヒントとして役立つのです。
定期的な研修と振り返りの重要性
安全な活動を一時的なものにせず、継続して根付かせるには「振り返り」と「教育」が欠かせません。
とくに災害ボランティアのように、メンバーが流動的で、現場環境も毎回異なる場合は、「その都度、安全文化を再構築する努力」が求められます。
そのために、多くの団体で実施されているのが次のような取り組みです。
1. 月1回の安全研修(シミュレーション型)
写真やイラストを使い、実際の災害現場を想定したKYTを実施。
過去の事例をもとに「この作業、どこが危険?」というワークショップ形式で考えます。
2. 作業終了後のミニ振り返り会(10分間)
「今日はどんな危険があったか?」をメンバー全員で共有。
改善点や反省点を可視化することで、次の活動につながります。
3. 新人向けの安全講習(入門編)
災害現場でよく使う道具や、装備品の使い方などを30分で説明。
SLシリーズやQQラダーの実物に触れてもらうことで、体感的に学べる場とします。
4. チェックリスト形式の自己点検シートの導入
活動前・後に記入することで、自分自身の安全意識を振り返る習慣がつきます。
こうした取り組みを「一過性のイベント」にせず、日常業務や地域活動と連動させることが、災害時に即応できる安全文化を育てることにつながります。
いざというときのために――
そして「助ける人」自身が安全であるために、日頃の備えこそが命を守るのです。
まとめ
災害ボランティアとして現地に赴くということは、ただ「手伝う」だけではありません。
現場に入る以上、自分自身の安全を確保する責任も同時に負っているということです。
この記事では、災害ボランティアにおける安全確保の基本として、
- よくある事故とその背景
- 災害現場特有のリスクと安全行動の原則
- 特殊梯子の正しい使い方と製品選び
- 危険予知トレーニング(KYT)の活用法
- 現場で安全意識を高める仕組みづくり
これらを具体的にご紹介してきました。
中でも、特殊梯子の使用は、想像以上に多くの現場で必要とされています。
しかし、使い方を誤れば大きな事故につながる可能性もあります。
だからこそ、設置角度の確認、三点支持の徹底、声掛けの習慣化といった、基本に忠実な行動が重要なのです。
また、KYTを活用すれば、事故の芽を事前に発見し、全員で共有することができます。
チームで「危険を予測し、未然に防ぐ」文化を育てることが、結果的に多くの命を守ることにつながるのです。
あなたの「こんな梯子があったらいいな」を、
カタチにします!
みなさん、お読みいただきありがとうございます!
私たち特殊梯子製作所は、みなさんの「あったらいいな」を形にする、梯子のスペシャリスト集団です。
🔧 こんなお悩み、ありませんか?
- 既製品の梯子では作業がやりにくい
- 特殊な場所での作業に適した梯子が見つからない
- より安全で使いやすい梯子が欲しい
そんなお悩み、私たちにお任せください!
1996年の創業以来、官公庁や大手企業様向けに数々の特殊梯子を製作してきた実績があります。
✨ 特殊梯子製作所ができること
- オーダーメイドの梯子製作
- アルミ、ステンレス、鉄など多様な素材対応
- 安全性と作業効率を両立した設計
あなたのアイデアや要望をお聞かせください。私たちの技術と創意工夫で、最適な梯子をカタチにします!
あなたの作業を、もっと安全に、もっと快適に。
特殊梯子製作所は、みなさんの「あったらいいな」を応援します!


