2025年9月9日
鉄道会社はなぜ「3分で60人」の避難性能を求めるのか?非常脱出はしごの知られざる設計要件

皆さんも、電車が緊急停止したというニュースを見て、「もし自分が乗っていたらどうやって避難するんだろう?」と考えたことはありませんか?
実は、鉄道車両からの避難には「3分で60人」という、あまり知られていないけれど非常に重要な目標性能があるんです。
今回は、私たちのような、いわば「縁の下の力持ち」が、皆さんの安全をどのように支えているのか、その裏側をお話しします。
なぜ「3分」なのか?
なぜ「60人」なのか?
そして、その厳しい要求を満たすために、非常脱出はしごにどんな工夫が隠されているのか。
技術者の視点から、その秘密を一緒に紐解いていきましょう。
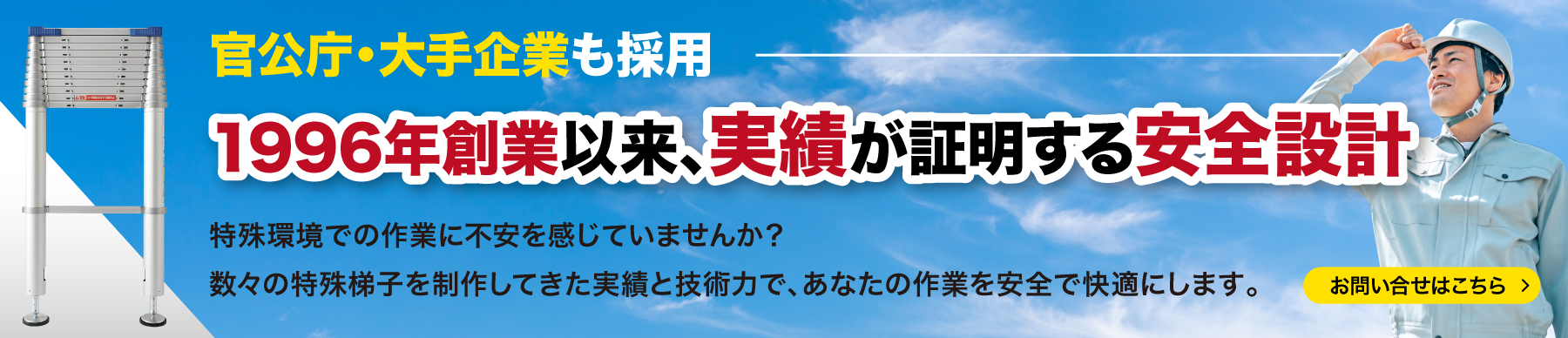
なぜ「3分で60人」?鉄道の避難基準、その数字の裏側
「3分で60人」という数字、なんだかキリが良いだけのように聞こえるかもしれませんね。
でも、この数字には、人の命を守るための科学的な根拠がしっかりと詰まっています。
ポイント1:火災と煙の恐怖から生まれた「3分」という時間
まず「3分」という時間。
これは、万が一、車両で火災が発生したケースを想定しています。
火災で最も恐ろしいのは、炎そのものよりも煙なんです。
煙はあっという間に広がり、数分で車内を危険な状態にしてしまいます。
専門的なデータによると、火災発生から煙や有毒ガスが充満し、避難が極めて困難になるまでの時間は、およそ3分から5分と言われています。
つまり「3分」という時間は、安全に避難できる限界から逆算された、命のタイムリミットというわけです。
この時間を超えてしまうと、一酸化炭素中毒などで命を落とす危険性が急激に高まります。
だからこそ、鉄道会社は「3分」という厳しい目標を掲げ、迅速な避難を実現しようとしているのです。
ポイント2:1車両の乗客数を考慮した「60人」という人数
次に「60人」という人数についてです。
これは、鉄道車両の定員や、実際の避難訓練の結果から導き出された、とても現実的な数字なんですよ。
皆さんが普段乗っている通勤電車は、1両あたり140人から160人くらいが定員です。
もちろん、緊急時に全員がひとつのドアから逃げるわけではありません。
複数のドアを使って避難することを想定し、ひとつのドア(はしご1台)あたり、どれくらいの人数をスムーズに誘導できるか。
これを計算した結果が「60人」という数字なんです。
実際の避難訓練でも、1車両の乗客約60人がはしごを使って避難するのに、ちょうど3分くらいかかったという報告もあります。
ラッシュ時のような混雑した状況も考慮し、パニックを起こさず安全に避難できる人数として、この「60人」という目標が設定されているんですね。
「3分で60人」を実現する!非常脱出はしごの設計と思想
さて、この厳しい目標を達成するために、私たちのようなメーカーが作る非常脱出はしごには、たくさんの技術と工夫が詰め込まれています。
まさに、技術者の知恵の結晶と言えるんです。
設計の工夫①:軽さと強度の両立「アルミ合金」という選択
「はしごって、重くて運ぶのが大変そう…」そう思われるかもしれませんね。
でも、非常脱出はしごの多くは、女性の乗務員さんでも一人で運べるように、とても軽く作られています。
その秘密は、素材にあります。
多くのはしごは「アルミ合金」でできているんです。
アルミ合金は、軽いだけでなく、とても丈夫なのが特徴です。
つまり、乗務員さんが素早く運べる「軽さ」と、たくさんの乗客が一度に使っても壊れない「強度」という、一見すると矛盾するような要求を両立できる優れた素材なんです。
この軽さと強度の絶妙なバランスを突き詰めるのが、私たち技術者の腕の見せ所でもあるんです。
設計の工夫②:一刻を争う現場での「迅速な設置性」
緊急時に「はしごの組み立て方が分かりません…」なんてことになったら、元も子もありませんよね。
そのため、今のはしごは、誰でも、直感的に、そして一瞬で設置できるように設計されています。
昔は部品を組み立てるタイプのはしごもありましたが、今はワンタッチで使える一体型や折りたたみ式が主流です。
例えば、手すりをカチッと持ち上げると、ステップ(足をかける部分)が自重でパラパラと広がり、自動的にロックされる仕組みになっています。
これなら、1秒を争う現場でも、迷うことなく確実に設置できますよね。
こうした「誰でも使える」というシンプルな操作性の裏には、実は複雑なメカニズムが隠されていて、開発には多くの試行錯誤がありました。
設計の工夫③:パニックを防ぐ「人間工学に基づいたデザイン」
避難時には、多くの人が不安や恐怖を感じています。
そんな中で、高さのあるはしごを降りるのは、とても怖いことかもしれません。
そこで、はしごには乗客の不安を少しでも和らげるための工夫が凝らされています。
これは「人間工学」という学問に基づいたデザインです。
人間工学とは?
人間の身体的な特徴や心理的な特性に合わせて、機械や道具、環境などをデザインし、より安全で使いやすいものにするための学問です。
例えば、以下のような工夫があります。
握りやすい手すり
太すぎず細すぎず、自然なカーブを描く手すりは、しっかり握ることで安心感を与えます。
滑りにくいステップ
ステップの表面には溝などの滑り止め加工が施され、雨の日でも安全に降りられるようになっています。
前向きで降りられる構造
後ろ向きで降りるのは心理的な抵抗が大きいですが、前を向いたまま降りられる設計にすることで、恐怖心を和らげ、スムーズな避難を促します。
こうした細やかな配慮の一つひとつが、パニックを防ぎ、安全な避難を実現するために不可欠なんです。
実際の現場ではどう使う?設置から避難までの流れ
では、実際に緊急事態が発生した場合、はしごはどのように使われるのでしょうか。
その流れをステップごとに見ていきましょう。
ステップ1:どこにある?意外と知らない「はしごの収納場所」
非常脱出はしごは、普段は皆さんの目につかない場所に、コンパクトに収納されています。
代表的な場所は、座席の下や、車両の端にある専用の収納箱の中です。
なぜその場所なのかというと、すぐに取り出せて、かつ避難の邪魔にならないからです。
限られたスペースに、いかにして必要な機能を持つはしごを収めるか。
これも、設計者の悩みのひとつなんですよ。
ステップ2:乗務員による迅速な設置作業
緊急時には、まず乗務員がはしごを収納場所から取り出します。
そして、開いたドアの床部分にあるレールなどに、はしごの上部をしっかりと固定します。
固定が完了したら、はしごを車両の外に押し出すだけ。
あとは先ほど説明したように、はしごが自動的に展開し、地面に設置されます。
訓練された乗務員の方なら、この一連の作業を、わずか数十秒で完了させてしまうそうです。
まさにプロの技ですね。
ステップ3:乗客の安全な避難誘導
はしごの設置が完了すると、いよいよ乗客の避難が始まります。
乗務員の指示に従い、落ち着いて一人ずつはしごを降ります。
この時、お年寄りや小さなお子さん、手荷物を持っている方などへの配慮がとても重要になります。
周りの乗客と助け合いながら、安全に地上へ降りることが大切です。
私たち安全機材の専門家から見ても、最終的に安全を確保するのは、こうした人と人との協力だと感じています。
鉄道の安全技術を、あなたの暮らしの中へ
ここまで鉄道という特殊な現場で活躍するはしごについてお話ししてきましたが、実は、ここで培われた技術や思想は、皆さんの暮らしや仕事の現場で役立つ、様々なはしごにも活かされているんです。
私たち特殊梯子製作所が、自信を持ってお届けする製品の一部を少しだけご紹介させてください。
特許技術の結晶!伸縮はしご「スーパーラダー」
鉄道用はしごに求められる「誰でも扱える軽さ」と「コンパクトな収納性」。
この技術を突き詰めて生まれたのが、当社の代名詞ともいえる伸縮はしご「スーパーラダー」です。
普段は平均90cmほどに縮めておけるのに、使うときには最大で5〜6mもの長さまで伸びるんです。
この独自の伸縮技術は特許も取得しており、その機能性とデザイン性から「グッドデザイン賞」も受賞しました。
プロの建築現場から、ご家庭でのちょっとした高所作業やDIYまで、あらゆる場面で活躍する一本です。
「もしも」に備える、家庭用避難はしご「QQラダー」
この記事を読んで、「電車の安全も大事だけど、自宅の備えはどうだろう?」と考えた方もいらっしゃるかもしれませんね。
そんな方におすすめなのが、マンションやご自宅の窓・ベランダの手すりに引っ掛けるだけで使える、緊急避難用はしご「QQラダー」です。
鉄道用はしごと同じく、いざという時に誰でも素早く使えることを第一に考えて設計されています。
普段はコンパクトに収納しておけるので、場所も取りません。
ご家族の安全を守る「もしも」への備えとして、ぜひご検討いただきたい製品です。
「こんなものまで?」を実現するオーダーメイド対応
私たちの強みは、なんといっても「世の中にないなら、創ってしまう」という開発力です。
実は、警察の特殊部隊で使われる「二人用はしご」や、陸上自衛隊で採用されている荷物運搬用の「背負板」なども、私たちが開発・製造しています。
「こんな高さに合うはしごが欲しい」「この作業をもっと安全にできる足場はないか?」
そんな現場の声に一つひとつお応えし、年間で500件以上のご相談をいただいています。
「考えることを辞めなければ不可能はない」という信念のもと、これからも世界に一つだけのはしごを創り続けていきます。
よくある質問(FAQ)
ここで、皆さんからよくいただく質問にお答えしますね。
Q: 新幹線やトンネル内での避難はどうなるのですか?
A: いい質問ですね。
新幹線は高架上を走ることが多いため、はしごもその高さに合わせた専用のものが用意されています。
また、長いトンネルの中では、はしごだけでなく、トンネルの壁に設けられた避難用の通路へ誘導される仕組みになっています。
場所の特性に合わせて、何重もの安全対策が考えられているんですよ。
Q: はしごは重くないのですか?女性の乗務員でも運べますか?
A: ご安心ください。
先ほどお話ししたように、素材に軽いアルミ合金を使うなどして、女性でも一人で運べる重さ(一般的に10〜15kg程度)になるよう設計されています。
軽さと、たくさんの人が乗っても大丈夫な強度を両立させるのが、私たち技術者のこだわりなんです。
Q: 子供やお年寄りでも安全に降りられますか?
A: はい、そのための工夫がたくさん詰まっています。
怖さを感じにくいように手すりが付いていて、前向きのまま降りられるようになっていますし、ステップの幅も広く、滑りにくい加工がされています。
もちろん、緊急時には乗務員や周りの乗客がサポートすることも大切ですね。
Q: 法律や省令で設置は義務付けられているのですか?
A: はい、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」という決まりで、非常時に乗客が安全に避難できる設備の設置が定められています。
「3分で60人」という数字は、この省令の要求を満たすための具体的な性能目標として、鉄道業界で設定されている基準と考えると分かりやすいかもしれません。
まとめ
「3分で60人」という数字の裏側、いかがでしたでしょうか。
この記事のポイントをまとめますね。
- 「3分」は火災時の煙から命を守るための科学的根拠に基づいた時間
- 「60人」は車両の定員や訓練に基づいた現実的な避難人数
- はしごには「軽さ・強度・設置性・安全性」を実現する技術者の工夫が満載
私たちが開発する非常脱出はしごは、普段は車両の片隅で静かに出番を待つ、まさに「縁の下の力持ち」です。
しかし、万が一の際には、皆さんの安全を確保する最後の砦となります。
この記事を通して、普段目にすることのない安全設備に少しでも興味を持っていただけたら幸いです。
そして、次に電車に乗るとき、この「縁の下の力持ち」の存在を少しだけ思い出していただけると、技術者としてこれほど嬉しいことはありません。
あなたの「こんな梯子があったらいいな」を、カタチにします!
みなさん、お読みいただきありがとうございます!
私たち特殊梯子製作所は、みなさんの「あったらいいな」を形にする、梯子のスペシャリスト集団です。
🔧 こんなお悩み、ありませんか?
- 既製品の梯子では作業がやりにくい
- 特殊な場所での作業に適した梯子が見つからない
- より安全で使いやすい梯子が欲しい
そんなお悩み、私たちにお任せください!
1996年の創業以来、官公庁や大手企業様向けに数々の特殊梯子を製作してきた実績があります。
✨ 特殊梯子製作所ができること
- オーダーメイドの梯子製作
- アルミ、ステンレス、鉄など多様な素材対応
- 安全性と作業効率を両立した設計
あなたのアイデアや要望をお聞かせください。私たちの技術と創意工夫で、最適な梯子をカタチにします!
あなたの作業を、もっと安全に、もっと快適に。
特殊梯子製作所は、みなさんの「あったらいいな」を応援します!


