2025年7月24日
【シニア世代の住まい】安全第一の高所作業〜高齢者向け梯子の選び方と使用上の注意点〜

「庭の松の枝が少し伸びてきたな…」
「高い棚の奥にある、あの箱を取りたい」
「リビングの切れた電球を交換しないと…」
暮らしの中のこうした場面で、若い頃と同じ感覚で、ついつい脚立や梯子にひょいと乗っていませんか?
実は、はしごや脚立からの転落事故は60代以上で急増し、大きな怪我につながりやすいという、見過ごせないデータがあるんです。
これは、ご自身の注意深さだけではカバーしきれない、年齢による身体の変化も関係しています。
この記事では、シニア世代の皆さんが安全に高所作業を行うための「本当に安全な梯子の選び方」と「ヒヤリハットを防ぐ使い方のコツ」を、専門的な視点から分かりやすく解説します。
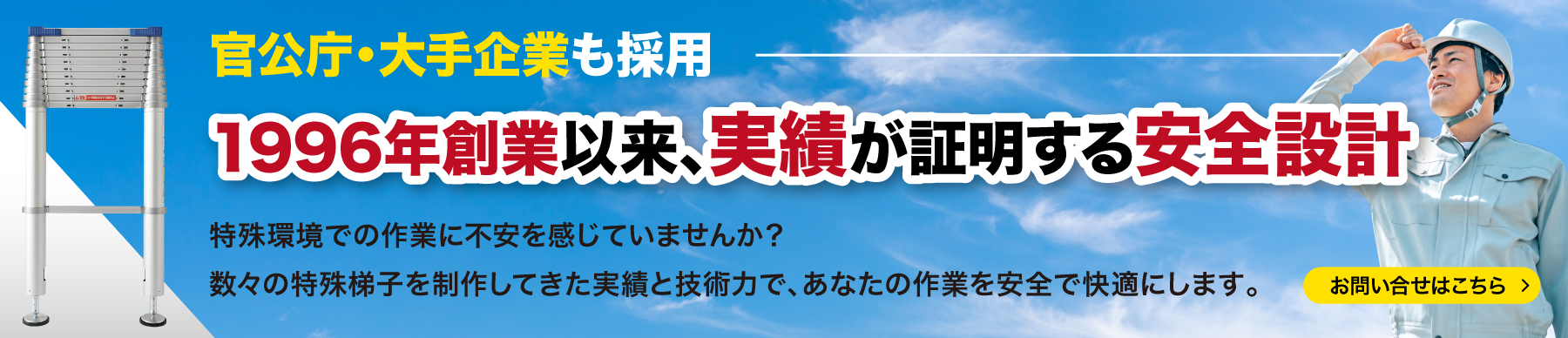
なぜ今、シニア世代の梯子・脚立選びが重要なのか?
「自分は大丈夫」が一番危ない!データで見る高齢者の転落事故
「自分はまだまだ元気だから大丈夫」。
そう思っている方ほど、一度立ち止まって考えてみてほしいのです。
製品評価技術基盤機構(NITE)の調査によると、2017年度から2021年度に発生したはしご・脚立の事故のうち、なんと約4割が60歳以上の方によるものでした。
そして、その事故のほとんどが「転落」で、半数近くが骨折などの重傷に至っています。
若い頃と比べて、高齢になってからの転倒・転落は、頭部や胴体を負傷する割合が高く、重症化しやすいという厳しい現実があります。
これは決して脅しではありません。
安全な暮らしを続けるために、まずはこの事実をしっかりと受け止めることが大切です。
若い頃との違いとは?高所作業に潜むリスク
「昔はこれくらい、なんてことなかったのに…」。
そう感じることが増えていませんか?
年齢を重ねると、自分では気づきにくい身体の変化が訪れます。
- バランス感覚の低下:視力や、平衡感覚を司る耳の奥(内耳)の機能が少しずつ衰えてきます。
- 反応の遅れ:足裏の感覚が鈍くなり、とっさの時に足が出にくくなったり、体勢を立て直しにくくなります。
- 筋力の低下:特に体を支える足の筋力が落ちることで、ふらつきやすくなります。
これらの変化は、誰にでも起こりうることです。
若い頃は自分の身体能力でカバーできた不安定さも、今は難しくなっているのかもしれません。
つまり、ご自身の注意深さだけに頼るのではなく、道具の側で安全性をしっかりと補ってあげるという考え方が、これからの高所作業には不可欠というわけです。
【梯子の専門家が解説】安全な高齢者向け梯子・脚立選び 3つのポイント
では、具体的にどんな梯子や脚立を選べば良いのでしょうか。
産業用の安全機材に長年携わってきた専門家として、絶対に外せない3つのポイントをお伝えします。
ポイント1:何よりも「安定性」!倒れにくさの秘密
高所作業で一番怖いのは、グラつくことによる転倒です。
この「安定性」は、いくつかの要素で決まります。
脚の開きと脚キャップ
脚が適切な角度(一般的に75度以下)でしっかりと開き、地面と接する「脚キャップ」が重要です。
最近では、床を傷つけにくく、滑りにくいエラストマーというゴム系の素材が使われているものがおすすめです。
ステップ(踏みざん)の幅
足を乗せるステップの幅が広いと、足全体で体を支えられるため、安定感が増します。
補助脚(アウトリガー)
特に屋外で使う場合、地面が平らでないこともあります。
そんな時に、本体の脚の外側に取り付けて安定性を高める「アウトリガー」という補助脚が付いていると、格段に倒れにくくなります。
ただ頑丈なだけでなく、こうした細部まで計算された安全設計が施されているかどうかが、プロの視点から見た良い製品の証です。
ポイント2:出し入れが億劫にならない「軽さと扱いやすさ」
「重くて物置から出すのが大変…」。
そんな理由で、つい椅子などを踏み台代わりにしてヒヤリとした経験はありませんか?
安全な道具も、使われなければ意味がありません。
だからこそ、無理なく扱える「軽さ」も大切な選択基準です。
現在、家庭用の脚立の多くはアルミ製で、非常に軽く作られています。
製品によっては3kgを切るものもあり、女性やシニア世代の方でも片手で持ち運べるものが増えています。
購入前には、ぜひ一度お店で実際に持ち上げてみて、「これなら自分でも気軽に出し入れできるな」と感じる重さのものを選んでください。
折りたたんだ時に薄くなるタイプなら、収納場所にも困りません。
ポイント3:安心感をプラスする「手すり」と「幅広ステップ」
シニア世代の脚立選びで、私が特に重要だと考えているのが、このポイントです。
昇り降りする際に体を支えてくれる「手すり」や、最上段での作業中に体を預けられる「上枠」が付いているタイプは、万が一のふらつきを防いでくれるだけでなく、「ここに掴まれる」という心理的な安心感が全く違います。
また、ポイント1の安定性とも関連しますが、足を乗せるステップの幅が広い「幅広ステップ」もおすすめです。
足裏全体でしっかりと踏ん張れるため、バランスが取りやすく、少し長い時間の作業でも足が疲れにくいというメリットがあります。
【専門家のおすすめ】手すり付きで安心!特殊梯子製作所の「伸縮ロフトはしご」
ここまでご説明したポイントを踏まえて、「例えばどんな製品があるの?」と思われたかもしれません。
当社、特殊梯子製作所でも、まさにシニア世代の皆さんに安心してお使いいただけるような製品を作っています。
その一つが「伸縮ロフトはしご(手すり付きタイプ)」です。(手すりなしもあります)

もともとはロフトへの昇り降りのために開発したものですが、その安全設計が、室内の高所作業にもぴったりなんです。
1. 安心の手すり
昇り降りの際にしっかりと体を支えられる、専用の手すりを付けられます。
2. コンパクト収納
独自の伸縮技術で、使わない時は小さく縮めてクローゼットなどにも収納できます。持ち運びが楽なのも嬉しいポイントです。
3. オーダーメイド感覚
設置する場所の高さに合わせて長さを調整できるので、ご自宅の環境に最適な一台をご用意できます。
「こんな梯子があったらいいな」というお客様の声に応えるのが、私たちのような専門メーカーの仕事です。
こうした製品も、選択肢の一つとして知っていただけると嬉しいです。
こんな作業にはこのタイプ!用途別おすすめ梯子・脚立
ひとくちに「はしご」と言っても、用途によって最適な形は異なります。
ここでは代表的な作業シーンごとにおすすめのタイプをご紹介します。
室内の電球交換や棚の整理には「ステップスツール(踏み台)」
室内のちょっとした高所作業には、1段から3段程度の「ステップスツール」と呼ばれる踏み台が最適です。
特に、上部に手すりが付いているタイプや、一番上の天板が広くて腰掛けられるようなタイプは、安定感があり安心して使えます。
最近では、リビングやキッチンにそのまま置いておいてもインテリアに馴染む、おしゃれなデザインのものもたくさん出ています。
庭の手入れや窓拭きには「安定性の高い軽量脚立」
庭木の剪定や屋外の窓拭きなど、地面が土や砂利で必ずしも平らではない場所で使う場合は、室内用よりもさらに高い安定性が求められます。
- 伸縮脚タイプ:4本の脚の長さをそれぞれ調整でき、段差や傾斜がある場所でも水平に設置できる脚立。
- アウトリガー付き:前述した、横への転倒を防ぐ補助脚が付いたタイプ。
これらの機能を備え、かつサビに強いアルミ製の軽量な脚立がおすすめです。
【注意】シニア世代が避けるべき梯子のタイプ
一方で、シニア世代の方にはあまりお勧めできないタイプもあります。
それは、壁などに立てかけて使う「一本はしご」です。
このタイプは、安全な設置角度である75度を保つのが難しく、足元が滑って転倒するリスクが非常に高いのです。
また、脚立を広げずにはしごとして使う「兼用タイプ」も、構造を正しく理解せずに使うと事故につながりやすいため、注意が必要です。
特別な理由がない限りは、自立する専用の脚立や踏み台を選ぶことを強く推奨します。
事故を防ぐ!梯子・脚立の正しい使い方 7つの鉄則
安全な製品を選んでも、使い方を間違えれば事故につながります。
製品を選ぶ際には、製品安全協会の「SGマーク」や軽金属製品協会の「Aマーク」など、安全基準を満たした製品の証があるかも確認しましょう。
その上で、以下の7つの鉄則を必ず守ってください。
- 使用前にグラつきや部品の破損がないか必ず点検する
- 開き止め金具は「カチッ」と音がするまで確実にロックする
- 設置場所は必ず平坦で滑りにくい場所を選ぶ
- 昇り降りは身体を梯子の中心に向け、両手を使う(三点支持の原則)
- 天板の上には乗らない、座らない、またがらない
- 身を乗り出して作業しない
- 体調がすぐれない時は絶対に使用しない
これらの基本を守るだけで、事故のリスクを大幅に減らすことができます。
よくある質問(FAQ)
ここでは、皆さんからよく寄せられる質問にお答えします。
Q: 梯子や脚立は何年くらいで買い替えるべきですか?
A: 使用頻度や保管状況によって大きく異なりますが、一つの目安として、屋外で雨風にさらされる場所に保管している場合は5〜7年、屋内保管でも10年を過ぎたら注意が必要です。
アルミ自体は錆びにくいですが、脚キャップなどの樹脂部品が紫外線で劣化することがあります。少しでもグラつきやきしみを感じたら、安全のために使用を中止し、買い替えを検討してください。
Q: どのくらいの重さのものがおすすめですか?
A: 一般的なご家庭で使うアルミ製の3段脚立であれば、3kg〜5kg程度のものが多いです。 大切なのは数字よりも、ご自身が「これなら無理なく持てる」と感じるかどうかです。購入前には、ぜひ店舗などで実際に持ち上げてみることを強くおすすめします。
Q: 手すりは片側だけでも十分ですか?
A: はい、片側にあるだけでも安全性は格段に向上します。もちろん、両側に手すりがある方がより安心ですが、収納スペースや作業内容との兼ね合いで選びましょう。重要なのは、昇り降りの際に必ずどちらかの手で手すりを掴む意識を持つことです。
Q: おしゃれなデザインのものは安全性が低いのでしょうか?
A: そんなことはありません。最近は、デザイン性と安全性を両立させた製品がたくさん開発されています。選ぶ際には、見た目だけでなく、これまでお話ししてきた「安定性」のチェックポイント(脚キャップの素材、ステップの幅など)や、「SGマーク」などの安全基準を満たしているかをしっかりと確認することが大切です。
Q: 家族が高齢で、脚立を使うのを止めさせたいのですが…
A: これは非常に難しい問題ですね。頭ごなしに「危ないからダメ!」と禁止してしまうと、かえって隠れて古い道具を使い続け、事故につながるケースもあります。
まずは「危ないから」ではなく、「もっと楽に作業できる、安全な道具があるみたいだよ」という視点で、この記事を一緒に読んでみてはいかがでしょうか。その上で、ご本人が行う作業に合った、より安全な新しい脚立をプレゼントするのも、素晴らしい解決策だと思います。
まとめ
今回は、シニア世代の皆さんが安全に高所作業を行うための梯子・脚立の選び方と使い方について、専門家の視点から解説しました。
最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 選び方の3大ポイント
- 倒れにくい「安定性」(脚キャップ、幅広ステップ)
- 扱いやすい「軽さ」(アルミ製など)
- 安心感を高める「手すりや上枠」
- 使い方の鉄則
- 使用前の点検と確実なロック
- 平らな場所への設置
- 天板には乗らず、無理な姿勢で作業しない
若い頃の感覚のまま、古い道具を使い続けることのリスクを理解し、今の自分に合った安全な道具を選ぶこと。
それは、ご自身と、あなたを大切に思うご家族の安心な暮らしを守るための、とても賢明な「投資」と言えます。
この記事を参考に、まずはご自宅にある脚立をチェックするところから始めてみませんか?
あなたの「こんな梯子があったらいいな」を、カタチにします!
みなさん、お読みいただきありがとうございます!
私たち特殊梯子製作所は、みなさんの「あったらいいな」を形にする、梯子のスペシャリスト集団です。
🔧 こんなお悩み、ありませんか?
- 既製品の梯子では作業がやりにくい
- 特殊な場所での作業に適した梯子が見つからない
- より安全で使いやすい梯子が欲しい
そんなお悩み、私たちにお任せください!
1996年の創業以来、官公庁や大手企業様向けに数々の特殊梯子を製作してきた実績があります。
✨ 特殊梯子製作所ができること
- オーダーメイドの梯子製作
- アルミ、ステンレス、鉄など多様な素材対応
- 安全性と作業効率を両立した設計
あなたのアイデアや要望をお聞かせください。私たちの技術と創意工夫で、最適な梯子をカタチにします!
あなたの作業を、もっと安全に、もっと快適に。
特殊梯子製作所は、みなさんの「あったらいいな」を応援します!


