2025年9月27日
別荘・セカンドハウスの維持管理に最適な「はしご」とは?プロが教える選び方

久しぶりに訪れた別荘、なんだか屋根に落ち葉がたくさん溜まっている…。
庭の木の枝も、ちょっと伸びすぎて隣の敷地にはみ出しそう…。
なんて経験はありませんか?
別荘やセカンドハウスは、日常から離れてリフレッシュできる特別な場所ですが、普段使わないからこそ、いざという時のメンテナンスが大変だったりしますよね。
特に、雨樋の掃除や木の剪定、高い場所の窓拭きなど、高所での作業は避けて通れません。
「大きなはしごを置いておくスペースはないし、かといって無いと困る…」
その気持ち、よく分かります。
この記事では、はしごメーカーの技術者である私が、別荘やセカンドハウスに最適な「コンパクトはしご」の選び方から、知っておくべき安全な使い方まで、プロの視点で徹底的に解説します。
【この記事の結論】別荘・セカンドハウス用はしご選び 失敗しないための3つの鉄則
- 鉄則1:なぜ「コンパクトはしご」が最適かを知る
別荘の限られたスペースでも収納しやすく、様々な作業場所へ楽に持ち運べるのが最大の魅力。一台で脚立にもなる「多機能タイプ」なら、あらゆる高所作業に対応できます。- 鉄則2:安全な製品を見極める3つのチェックポイント
「SGマーク」などの安全性はもちろん、メーカー独自の安全基準も確認しましょう。ご自身の体重+道具の重さを考慮した「耐荷重100kg以上」を目安に、安全の要である「ロック機構」が確実な製品を選び抜くことが重要です。- 鉄則3:シーン別の使い方と安全の基本を理解する
雨樋の掃除では壁に立てかけ、庭木の剪定では脚立として使います。壁に立てかける際は、地面との角度を「75度」に保つのが転倒を防ぐプロの鉄則です。
本文では、これらのポイントをプロの視点からさらに詳しく解説します。
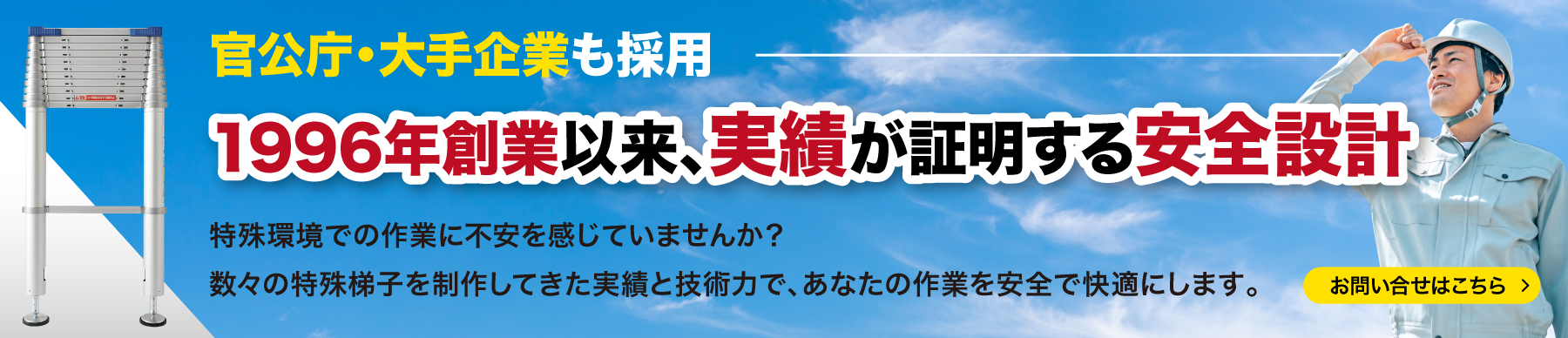
なぜ別荘・セカンドハウスには「コンパクトはしご」が最適なのか?
そもそも、なぜ大きなはしごではなく、コンパクトなタイプが別荘に向いているのでしょうか。
それには、ちゃんとした理由があるんです。
ポイントは3つあります。
ポイント1:保管スペースの問題。「普段使わない」からこそ収納性が重要
別荘の物置や収納スペースは、意外と限られていますよね。
バーベキューセットやアウトドア用品など、他にも収納したいものはたくさんあるはずです。
一般的な脚立や一連はしごは、頑丈ですがその分かさばるのが難点。
一方、伸縮式や折りたたみ式のコンパクトはしごなら、ぐっと小さく収納できます。
つまり、物置の隅やクローゼットの隙間、車のトランクにもすっきり収まるというわけです。
普段使わないものだからこそ、保管場所に困らないというのは大きなメリットなんですよ。
ポイント2:持ち運びの手軽さ。様々な作業場所に簡単に移動できる
別荘でのメンテナンス作業は、一箇所で終わらないことが多いものです。
- 建物の裏手で雨樋の掃除
- 庭の真ん中で木の剪定
- 室内で切れた電球の交換
こんな風に、作業場所は多岐にわたります。
重くて大きい従来のはしごでは、移動させるだけで一苦労ですよね。
その点、軽量なアルミ製のコンパクトはしごなら、女性やご年配の方でも比較的楽に持ち運べます。
ひょいと担いで移動できる手軽さは、面倒に感じがちなメンテナンス作業のハードルをぐっと下げてくれるんです。
ポイント3:多機能性。一台で脚立にもはしごにもなる万能タイプ
特に「折りたたみ式」と呼ばれる多関節タイプのはしごは、一台で様々な形状に変化させることができます。
まっすぐ伸ばして壁に立てかける「はしご」としてはもちろん、A字に開いて自立する「脚立」としても使えます。
別荘の敷地内には、玄関アプローチの階段など、段差がある場所も多いかもしれませんね。
そんな不安定な場所でも、片方の脚だけ縮めて段差に対応できる製品もあります。
これ一台あれば、別荘で想定されるほとんどの高所作業に対応できると言えるんです。
【はしごのプロが解説】コンパクトはしごの種類と構造的な特徴
さて、コンパクトはしごが便利なことはお分かりいただけたかと思います。
ここでは、代表的な種類とその構造的な特徴について、少しだけ専門的な視点から解説しますね。
伸縮はしご(テレスコピックラダー):まるで釣竿のように伸び縮み
「たけのこ式」なんて呼ばれ方もする、収納時に非常にコンパクトになるタイプです。
その構造は、まるで釣竿(テレスコープ)のよう。
パイプ状の支柱が何層にも重なっていて、引き出すことで長く伸びていきます。
各段にロック機構が備わっており、必要な高さにぴったり調整できるのが最大の魅力です。
ただし、このロック機構の信頼性が、はしご全体の安全性を左右する心臓部になります。
ここがしっかりしていない製品は、絶対に選んではいけません。
例えば、私が開発に携わっている『スーパーラダー』という製品は、独自の特許技術で伸縮の操作性と安全性を両立させています。
平均90cmまでコンパクトに縮まるのに、最大で5〜6mまで伸びるため、別荘の物置にもすっきり収まりますよ。

折りたたみはしご(多関節はしご):変幻自在のトランスフォーマー
複数のパーツがヒンジ(関節)で繋がれていて、折りたたんだり伸ばしたりできるタイプです。
カチ、カチッと関節部分のロックを操作することで、様々な形状に変化させられます。
脚立、はしご、さらには作業用の足場(作業台)にもなる製品もあり、まるで変幻自在のトランスフォーマーのようでしょう?
このタイプで重要なのは、ヒンジ部分の強度とロックの確実性です。
作業の荷重が集中する部分なので、ここの作りがしっかりしているかがポイントになります。
薄型設計のステップスツール(脚立):インテリアにもなる手軽さ
室内でのちょっとした高所作業、例えば電球の交換や、高い棚の上にある荷物の出し入れなどに最適なのがこのタイプです。
折りたたむと数センチの薄さになる製品も多く、デザイン性の高いものなら、お部屋の片隅にそのまま置いておいてもインテリアの邪魔になりません。
手軽で便利な反面、あくまで簡易的な作業用と考えるべきです。
屋外での本格的な雨樋掃除や、壁の補修といった作業には、より安定性の高い伸縮はしごや折りたたみはしごを選ぶようにしてくださいね。
【最重要】安全のプロが教える!失敗しないコンパクトはしごの選び方
ここからが、この記事で最もお伝えしたいことです。
便利でコンパクトなはしごですが、一歩間違えれば大きな事故につながる道具でもあります。
安全な製品を見極めるための3つのチェックポイントを、ぜひ覚えてください。
チェックポイント1:安全性の証をどう見極めるか?マークの意味とメーカーの姿勢
製品の安全性を判断する際、「SGマーク」や「JISマーク」は一つの分かりやすい目安になります。
これらは国や第三者機関が定めた基準をクリアした証です。
しかし、それが全てではありません。
特に、私たちのような特定の分野を専門とするメーカーは、その規格で定められた項目以上に、実際の現場で起こりうる様々な状況を想定した、独自の厳しい安全基準を設けていることが多いのです。
大切なのは、マークの有無だけで判断するのではなく、そのメーカーがどのような思想で製品を作り、どんな安全試験を繰り返しているか、その姿勢を見ることです。
ウェブサイトで製品の構造的な特徴や、強度に関する情報をきちんと公開しているかどうかも、信頼できるメーカーを見極める重要なヒントになります。
つまり、製品の背景にある「安全へのこだわり」を感じ取ることが、本質的な安心につながるというわけです。
チェックポイント2:材質と耐荷重。「軽さ」と「強さ」のバランスを見極める
コンパクトはしごの主な材質は、軽くて錆びにくい「アルミニウム」です。
持ち運びやすさを考えるとアルミ製がおすすめですが、次に確認したいのが「最大使用荷重(耐荷重)」です。
これは「何kgまで耐えられますよ」という数値で、必ず製品に表示されています。
選ぶ際の目安は、「ご自身の体重+作業道具の重さ+α(余裕分)」です。
例えば体重70kgの人が5kgの道具を持つなら、耐荷重100kg以上のものを選ぶと安心です。
ここがポイントです。
耐荷重は、はしごの骨格の強さを示す非常に重要な数値なんです。
チェックポイント3:ロック機構の確実性。技術者が語る「ここを見ろ!」
伸縮はしごや折りたたみはしごの安全性の要、それがロック機構です。
ここの作りが甘いと、作業中に突然はしごが縮んだり、形が崩れたりする重大な事故につながります。
もしお店で実物を見られるなら、ぜひ実際に操作してみてください。
- スライド式のロックか、レバー式のロックか
- 「カチッ」と小気味よい音と共に、確実に固定される感触があるか
- ロックした状態で、支柱にガタつきはないか
指を挟みにくい構造になっているかなど、安全への配慮が設計に現れます。
ここは技術者として、特に注目してほしいポイントです。
別荘・セカンドハウスでの具体的な活用シーン別アドバイス
では最後に、具体的な作業シーンを思い浮かべながら、どんなはしごが適しているか、そして安全に使うためのコツをお話しします。
シーン1:屋根の点検・雨樋の掃除
軒先など、ある程度の高さが必要になるこの作業。
壁に立てかけて使うことになるため、安定した伸縮はしごや、はしご形状で使える折りたたみはしごがおすすめです。
立てかける際は、地面とはしごの角度が75度になるのが基本です。
角度が急すぎると後ろに倒れやすく、緩やかすぎると足元が滑りやすくなるからです。
これはプロの現場でも徹底されている安全の鉄則なんですよ。
シーン2:庭木の剪定・果実の収穫
地面が土や芝生で、少し不安定な場合が多いですよね。
こういう場所では、壁に立てかけるタイプよりも、A字に開いて四本の脚でしっかりと自立する「脚立」形状で使うのが断然有利です。
一方、太い枝をノコギリで切るような作業では、その反動でバランスを崩しやすくなります。
身体をはしごから大きく乗り出さないように注意してくださいね。
シーン3:外壁の補修や窓拭き
ペンキを塗ったり、窓を拭いたりと、比較的長い時間、両手を使って作業したい場面です。
こんな時は、多機能な折りたたみはしごを「作業台(足場)」の形状にして使うと非常に便利です。
足元が安定し、両手が自由に使えるようになるのが大きなメリット。
バケツやペンキ缶といった道具を置くスペースも確保できるので、作業効率が格段にアップします。
よくある質問(FAQ)
Q: 伸縮はしごは「危険」という話を聞きますが、本当ですか?
A: よくある疑問ですね。
結論から言うと、信頼できるメーカーが正しく製造し、それを正しく使えば非常に安全で便利な道具です。
危険とされる原因の多くは、安全への配慮が不十分な製品や、ロックの確認を怠るなどの誤った使い方にあります。
信頼できるメーカーの製品を選び、取扱説明書をしっかり読んで使うことが何よりも大切です。
Q: 女性や高齢者でも扱いやすい、軽いコンパクトはしごはありますか?
A: はい、あります。
アルミ製の2〜3段程度の薄型ステップスツールなら2〜3kg程度のものが多く、室内での利用に最適です。
屋外での作業も考えるなら、5〜7kg程度の軽量な伸縮はしごも選択肢になります。
大切なのは、ご自身の体力で無理なく安全に運べる重さのものを選ぶことです。
Q: はしごの寿命や、点検すべきポイントはありますか?
A: 保管状況にもよりますが、5〜10年が一つの目安と考えてください。
技術者としては、使う前に必ず以下の3点を確認する習慣をつけてほしいです。
- ロック機構がスムーズに、そして確実に動くか
- 支柱やステップ(踏みざん)に凹みや亀裂がないか
- 地面と接する脚のゴムキャップがすり減ったり、硬化したりしていないか
Q: はしごはどこで購入するのがおすすめですか?
A: 実際に製品を触って、重さやロック機構の操作感を確かめられるホームセンターがおすすめです。
専門の店員さんに相談できるのも心強い点です。
もしネット通販を利用する場合は、製品の仕様やメーカーの情報をよく確認し、信頼できる販売元から購入するようにしてください。
Q: 別荘で長期間保管する場合の注意点はありますか?
A: これは重要なポイントですね。
雨風や直射日光が当たらない、湿気の少ない屋内での保管を徹底してください。
特に伸縮はしごの内部に砂やホコリ、クモの巣などが入ると、ロック機構が正常に作動しなくなる原因になります。
使用後はきれいな布で拭いてから収納するだけで、はしごの寿命はぐっと長持ちしますよ。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
別荘・セカンドハウスの維持管理において、コンパクトはしごは非常に頼りになるパートナーです。
しかし、それは「安全」という土台があって初めて言えること。
この記事では、はしごメーカーの技術者として、単なる利便性だけでなく、最も重要な「安全な製品の選び方」について詳しく解説しました。
- ポイント1:メーカーの「安全へのこだわり」を見極める
- ポイント2:「耐荷重」を確認し、軽さと強さのバランスを考える
- ポイント3:安全の心臓部、「ロック機構」の確実性を確かめる
この3つのポイントをしっかり押さえることで、あなたは数ある製品の中から、本当に信頼できる一台を選び抜くことができるはずです。
正しい知識で賢いはしごを選び、安全なメンテナンスを行う。
それが、あなたの大切な別荘での時間を、より豊かで快適なものにしてくれると私は信じています。
次のステップとして、まずはご自宅の物置や車のトランクに、どのくらいのサイズなら収納できそうか、メジャーで測ってみることから始めてみてはいかがでしょうか。
あなたの「こんな梯子があったらいいな」を、カタチにします!
みなさん、お読みいただきありがとうございます!
私たち特殊梯子製作所は、みなさんの「あったらいいな」を形にする、梯子のスペシャリスト集団です。
🔧 こんなお悩み、ありませんか?
- 既製品の梯子では作業がやりにくい
- 特殊な場所での作業に適した梯子が見つからない
- より安全で使いやすい梯子が欲しい
そんなお悩み、私たちにお任せください!
1996年の創業以来、官公庁や大手企業様向けに数々の特殊梯子を製作してきた実績があります。
✨ 特殊梯子製作所ができること
- オーダーメイドの梯子製作
- アルミ、ステンレス、鉄など多様な素材対応
- 安全性と作業効率を両立した設計
あなたのアイデアや要望をお聞かせください。私たちの技術と創意工夫で、最適な梯子をカタチにします!
あなたの作業を、もっと安全に、もっと快適に。
特殊梯子製作所は、みなさんの「あったらいいな」を応援します!


